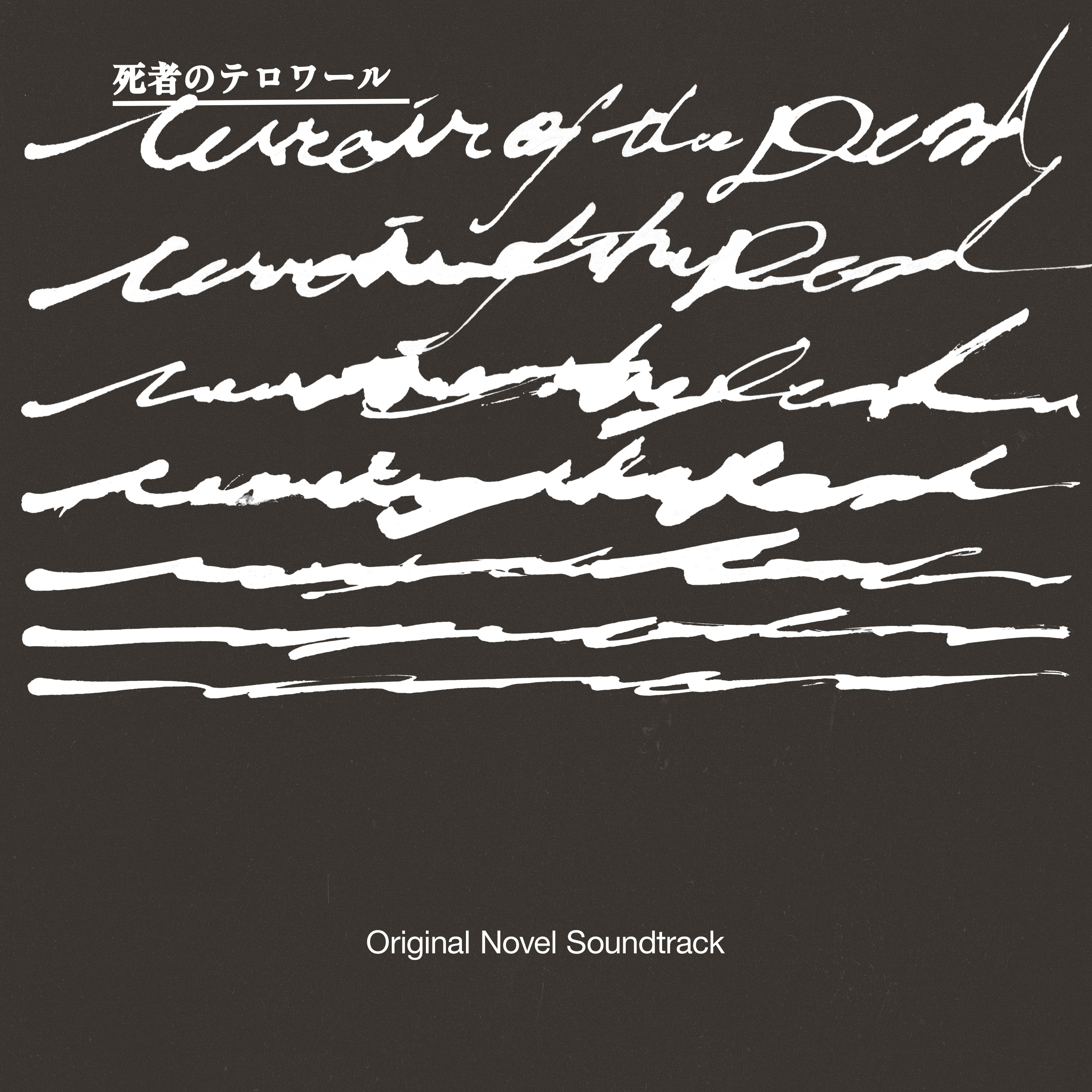2月のお休みのおしらせです。
1(日)
3(火)
10(火)
17(火)
18(水)
24(火)
2/1(日)は
『喫茶 アアニコ vol.3』
『駆け込みアアニコ vol.16』
のため、通常営業はお休みです。
曽根雅典『死者のテロワール』発売中です。
取り扱い書店と、その書店のオンラインショップでも購入できます。
『死者のテロワール・オリジナルノベルサウンドトラック』も配信しています。
よろしくお願いいたします。
2026/01/20 22:48 | Category:nicolas
『喫茶アアニコ』は、2月1日(日)の1日だけ開店する喫茶店です。
昨年に引き続き、3回目の開店です。
徳島・アアルトコーヒーの庄野さんがネルドリップでコーヒーを提供します。
コーヒーに合うケーキや軽食のセットをニコラが提供します。
営業時間は13時から17時まで。
ネルドリップのアアルトコーヒーを飲めるのは喫茶アアニコだけ。
この機会にぜひ飲みに来てください。
ご来店お待ちしております。
※普段のニコラのメニューはお休みです。
開店の13時のお時間のみ、ご予約を承ります。メールかお電話でお申し込みください。
その後のお時間は席が空き次第のご案内となります。ご了承ください。
『喫茶 アアニコ vol.3』
日時:2026年2月1日(日) 13時open~17時close
場所:nicolas(世田谷区太子堂4-28-10 鈴木ビル2F)
メニュー:ネルドリップコーヒー(14g/aalto coffee and the rooster 庄野雄治) ケーキ、軽食(nicolas)
予約:nicolas info@nicolasnicolas.com 03-6804-0425
2026/01/08 13:31 | Category:nicolas
毎度おなじみ駆け込みアアニコです。回を重ねてvol.16です。
駆け込みアアニコとは、アアルトコーヒーの庄野さんと、nicolasの曽根が
ただただ雑談をするというイベントです。
2017年の1月にはじまったこのイベントも、もう9年になります。
「人を、あるいは自分を、コンテンツとして消費し続けるこの世の中で
そうじゃないやり方で何ができるんだろう」
というようなことを話したりします。
というか、ずっとそれをやろうとしている雑談イベントです。
インターネットで世界をみると、もうめちゃくちゃな気がしてきます。
「詰んでる」感じがしてきてしまいます。
戦争だったり円安だったり。
今まで通り誠実に仕事をしているだけでは、生き残れないんじゃないかと不安になります。
とりあえず、身近にいる人たちと、いつも通り、
なんでもない生活の話をするところからはじめていきましょう。
『喫茶 アアニコ』のあと、夕方17時からの開催です。
よかったら、ぜひお越しください。
『駆け込みアアニコ vol.16』
2月1日(日) 17:00-18:30 1,000円(1ドリンク付)
場所:nicolas 世田谷区太子堂4-28-10 鈴木ビル2F
出演:庄野雄治(14g/aalto coffee and the rooster)×曽根雅典(nicolas)
ご予約:nicolas info@nicolasnicolas.com 03-6804-0425
2026/01/08 13:30 | Category:nicolas
1月のお休みのおしらせです。
1/1(木)~1/6(火)
13(火)
20(火)
21(水)
27(火)
曽根雅典『死者のテロワール』発売中です。
取り扱い書店と、その書店のオンラインショップでも購入できます。
『死者のテロワール・オリジナルノベルサウンドトラック』も配信しています。
12/30(火)~1/6(火)まで
年末年始休業をいただきます。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
2026/01/06 12:31 | Category:nicolas
12月のお休みのおしらせです。
2(火)
9(火)
16(火)
17(水)
22(月)
26(金)
30(火)
31(水)
12/20(土)、21(日)、23(火)、24(水)、25(木)の5日間は、
クリスマスコースのみの営業となります。
(通常営業はお休みです。)
曽根雅典『死者のテロワール』発売中です。
取り扱い書店と、その書店のオンラインショップでも購入できます。
『死者のテロワール・オリジナルノベルサウンドトラック』も配信しています。
12/30(火)~1/6(火)まで
年末年始休業をいただきます。
よろしくお願いいたします。
2025/11/20 14:11 | Category:nicolas
クリスマスコースのおしらせです。

12/20(土)、21(日)、23(火)、24(水)、25(木)の5日間は
クリスマスコース(要予約)のみの営業となります。
(※12/22(月)はお休みです。)
おひとりさま7700円(税込み)のコースとなります。
スタート時間は
①17:00~
②20:00~
になります。
クリスマスコースのご予約は、お電話にて承ります。
☎03-6804-0425
お席に限りがありますので、
定員に達し次第、受付終了とさせていただきます。
ご予約お待ちしております。
2025/11/20 14:09 | Category:nicolas
『死者のテロワール・オリジナルノベルサウンドトラック』
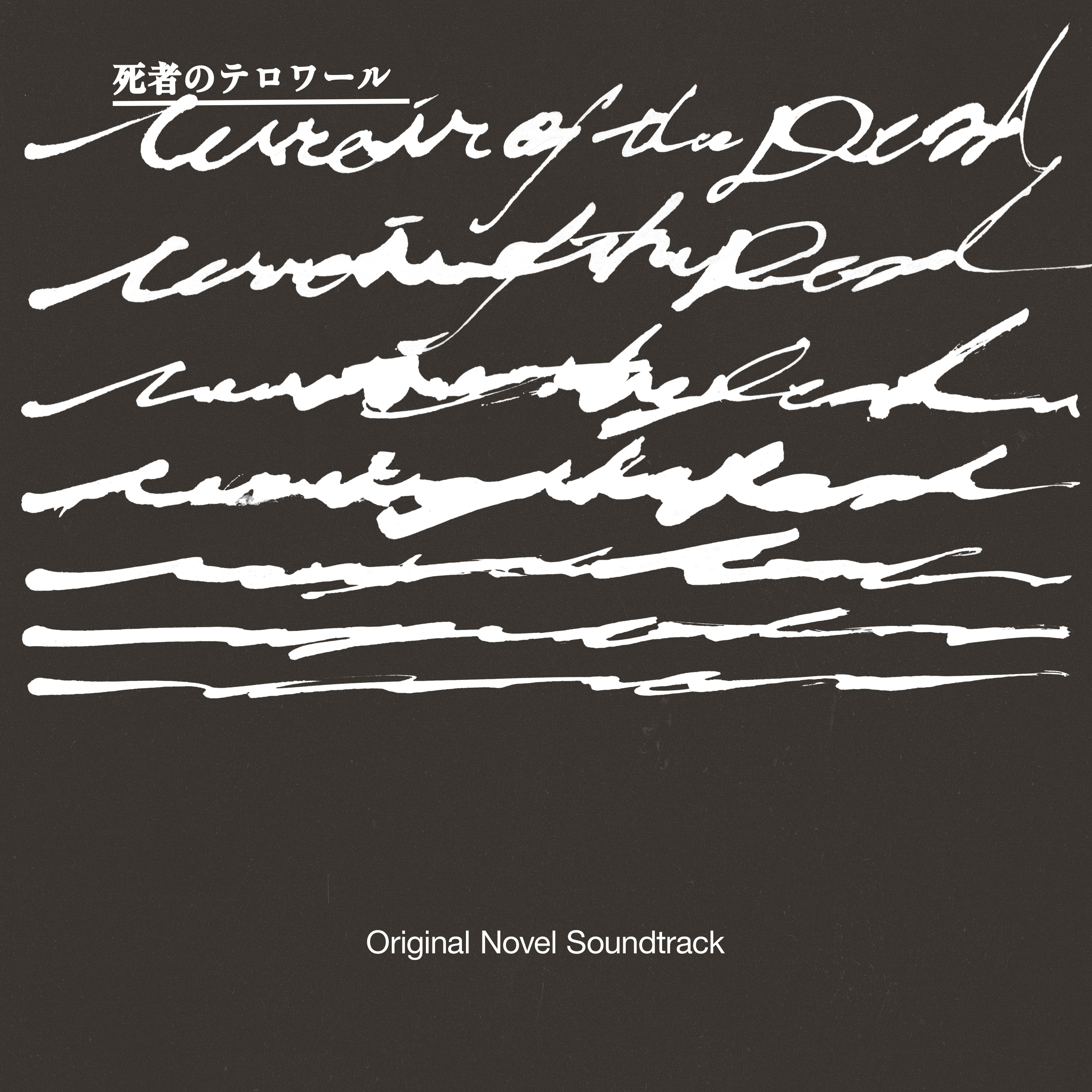
de.te.ri.o.ra.tion/Deterio Liber
2024年にDeterio Liberより刊行した小説、曽根雅典『死者のテロワール』をイメージソースとしたサウンドトラックアルバムが、2025年11月5日にデジタルリリースされました。以下、de.te.ri.o.ra.tion/Deterio LiberのHPよりの転載です。
2061年、ディストピアと化した日本。地方に作られた尊厳死のための施設にあるカフェ「クロエ」に集まる常連たちの、食べ物と記憶にまつわる回想の日々を描いた、SF的でありながらもノスタルジックな雰囲気を持つ作品の世界観をベースとした、静謐なアンビエントの名盤がここに完成しました。
de.te.ri.o.ra.tion/Deterio Liber主催の橋本竜樹、Ami Kawai、Naoya Takakuwaといった過去にリリースしているレーベルゆかりのアーティストに加え、ギターによる即興演奏で近年活躍目覚ましいMao Otake、Chee Shimizuとのユニット活動でも注目のmiku-mariが参加。更にはミュージシャン/アーティストとして活動する扇谷一穂、詩人の菅原敏が小説の一節の朗読で参加し、小説の世界観をより深く味わうことができる内容となっています。
小説を未読の方も、このサウンドトラックをきっかけに手にとっていただけると嬉しいです。
配信リンクはこちら
◆参加アーティストプロフィール(五十音順)
Ami Kawai/カワイアミ
PRINCE GRAVES名義でde.te.ri.o.ra.tionよりアナログアルバムと7インチシングルをリリース。
現在はOSHIDAAYA、新村隆慶らと即興演奏のライブ活動を行うほか、Ami Kawai名義での楽曲制作を行っている。
また、DJユニット「サントラブラザース」とともにサウンドトラックのみのDJ活動も行う。
Instagram
扇谷一穂/おおぎやかずほ
東京生まれ。幼い頃に習っていた謡いをきっかけに自分の声に興味を持ち、声を生かしたいと大学在学中にオリジナル曲を作り始める。卒業と同時に1st album 「しののめ」をMIDI creativeよりリリース。アートワークを手がける。レコードジャケットのデザインをしていた父の影響で音楽と絵画に垣根を感じることなく、音楽と絵画 2つの表現で心に広がる風景を自由に描いている。今までに4枚のアルバムをリリース。全国でライブ・展示を重ねる。発声を中心として、感じる心を育むこどものためのワークショップ・朗読・肖像を描くポートレートドローイングなど多岐にわたって活動している。
HP
菅原敏/すがわらびん
詩人。2011年、アメリカの出版社PRE/POSTより詩集『裸でベランダ/ウサギと女たち』をリリース。以降、執筆活動を軸にラジオでの朗読や歌詞提供、欧米やロシアでの朗読公演など幅広く詩を表現。近著に『かのひと 超訳世界恋愛詩集』(東京新聞)、『季節を脱いで ふたりは潜る』(雷鳥社)。最新詩集『珈琲夜船』(雷鳥社)。
Instagram
Naoya Takakuwa/ナオヤタカクワ
de.te.ri.o.ra.tionよりアナログアルバムをリリース後、Deterio Liberより音楽CD-R付き書籍『バナナコーストで何が釣れるか』を発表。
現在はバンドCõwazでボーカルギターを担当。
Profile
Tatsuki Hashimoto/橋本竜樹
de.te.ri.o.ra.tion/Deterio Liber主宰。
1999年に京都のインディーズレーベル”Bambini”から最初のレコードを発表、以降Nag Ar Juna名義で作品を発表している。また、編曲家、プロデューサーとしてChara、Yuki、カジヒデキ、Halfby、Minakekke等の作品に携わっている。
X
Mao Otake/大竹雅生
ギタリスト、音楽家。ギター等を用いてソロでの演奏活動を行っている。
Instagram
miku-mari/ミクマリ
2000年代前半より、ギターとギターシンセサイザー、デジタルデバイスや音具を用いた音響表現を探求する演奏活動を行うほか、音楽レーベル/コレクティブ「conatala」のメンバーとしても活動。近年はChee Shimizu + miku-mariとして、生成音楽プロセスと即興演奏による音空間の創出に取り組んでいる。
Instagram
◆マスタリング:Kazama Moe (studio Chatri)
◆ジャケットアートワーク:横山雄
◆楽曲情報
1.Terroir of the Dead – Mao Otake
2.Preface – miku-mari
3.朱夏 – Tatsuki Hashimoto
4.クロエ – Mao Otake
5.After the Silence – Tatsuki Hashimoto
6.鮎釣り – Naoya Takakuwa
7.クロエ(朗読)- Mao Otake feat. 菅原敏
8.Ash and Grapes – miku-mari
9.Echoes of Chloe – Tatsuki Hashimoto
10.ハレー彗星 – Ami Kawai
11.朱夏(朗読)-Tatsuki Hashimoto feat. 扇谷一穂
12.ここがある場所 – Ami Kawai
2025/11/05 15:42 | Category:nicolas
11月のお休みのおしらせです。
4(火)
11(火)
18(火)
19(水)
25(火)
29(土)
11/29(土)は
『別の、東京』
のため、通常営業はお休みです。
曽根雅典『死者のテロワール』発売中です。
取り扱い書店と、その書店のオンラインショップでも購入できます。
よろしくお願いいたします。
2025/10/23 16:13 | Category:nicolas
10月のお休みのおしらせです。
7(火)
14(火)
15(水)
21(火)
25(土)18:00~open
28(火)
曽根雅典『死者のテロワール』発売中です。
取り扱い書店と、その書店のオンラインショップでも購入できます。
よろしくお願いいたします。
2025/10/01 13:09 | Category:nicolas
9月のお休みのおしらせです。
2(火)
9(火)
16(火)
17(水)
23(火・祝)
26(金)
30(火)
9/26(金)は
「cine nicolas vol.1 アンナ・カリーナ主演『アンナ』with 佐々木誠スパイスカレー」
のため通常営業お休みです。
曽根雅典『死者のテロワール』発売中です。
取り扱い書店と、その書店のオンラインショップでも購入できます。
よろしくお願いいたします。
2025/08/27 15:33 | Category:nicolas